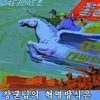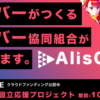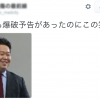どうも、上永です。
梅雨が明けたら、いよいよ本格的な夏が来る。2025年の夏だ。 メディアは相変わらず、どこか浮かれた調子で「消費喚起」だの「観光復興」だのと喧しい。 だが、その喧騒の裏で、この国が抱える根本的な病巣は、ますます深まっているように見える。
先日、とある記事を読んだ。 「2025年には、介護人材が約20万人不足する見込み」だという。 それから、「後期高齢者の人口が増加し、社会保障費がさらに増加する」とも。
何を今さら、という話だ。
誰もが分かっていたことではないか。 しかし、いざその「時」が目前に迫ると、途端に「問題」として認識される。 まるで、今まで見て見ぬふりをしてきたことのツケが一気に回ってきたかのように。
そして、そのツケを払わされるのは、決まって若い世代だ。
「少子化対策」と銘打たれた政策の数々は、聞こえはいい。 「経済的支援の強化」「児童手当の拡充」「育休の取得促進」・・・。 だが、それは本当に、この国の若者が「子どもを産み育てたい」と心から思えるような、根本的な社会の変革を伴うものなのだろうか。
確かに、目先の小銭が増えれば、いくらかは助かるだろう。 だが、彼らが本当に望んでいるのは、目の前の「小銭」ではない。
未来だ。
安定した雇用。物価高に負けない賃金。 そして、自分たちの人生を、他者に搾取されることなく自由に選択できる社会。 それら全てが、この国では「保証」ではなく「運」になっている。
AIが進化し、新たな仕事が生まれる一方で、「AI導入で仕事を失う不安がある」と答えた人が58%にも上る、という調査結果もある。 「AIスキルを持つ技術者は、持たない技術者と比較して47%高い給与を得ている」などという耳触りのいい話も聞くが、それはごく一部の人間だけが享受できる「特権」なのではないのか。
大多数の若者は、今、何を思い、何を感じているのか。 SNSを見れば、彼らの「本音」が溢れている。 「結婚? 無理でしょ」「子ども? 育てられるわけない」「未来に希望なんて持てない」。 絶望と諦念。それが、彼らのリアルな声だ。
そして、そんな彼らに向かって、「少子化だから子どもを産め」だの「若い者が頑張れ」だのと言うのは、あまりにも無責任ではないか。 それは、まるで「優しい嘘」を投げつけて、根本的な問題を覆い隠そうとしているようにしか見えない。
この国は、若者から「未来」を奪っておきながら、その「責任」だけは負わせようとしている。 その不均衡が、今の少子化の根源にある。
「一人ひとりの人権と個性が尊重され、人生の自由な選択ができる社会」。 日本共産党の綱領にもあるこの言葉は、まさに今の日本に最も欠けている部分だろう。 経済的・社会的事情によって、結婚や出産、ひいては自分自身の人生設計さえも「諦める」ことを強いられている若者が、どれだけいることか。
私たちが本当に取り組むべきは、上辺だけの小手先の対策ではない。 若者たちが「未来を描ける」ような、希望の持てる社会を築き上げることだ。
そのために、私たちは何をすべきか。 それは、彼らの「諦め」を「怒り」に変え、その怒りを政治にぶつける力を与えることだ。 若者が政治に関心を持ち、自らの手で未来を切り開くための具体的な道筋を示すこと。
若者の政治参加を促す取り組みが活発になっていることは、微かながらも希望の光だ。 しかし、その光を大きくするためには、私たち自身が、彼らの絶望に真摯に向き合い、その根本原因を取り除かねばならない。
この国の未来は、若者のなかに漂う「優しい嘘」に満ちた諦念を打ち破ることからしか始まらない。